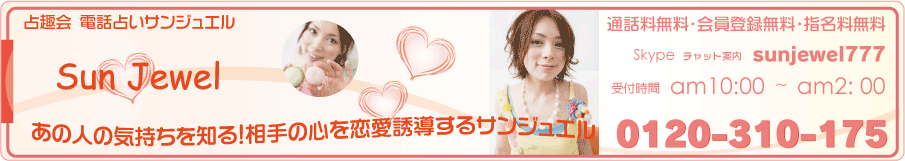| 命系占術 |
| 歴史 |
 |
紀元前400年~ 200年頃の蘭台御史が基にされている。 |
| 始祖 |
 |
不明 |
|
| 四柱推命とは |
 |
四柱推命という呼称は、中国の原書に見ることができない。日本独自のものであるが英語圏で"Four Pillars of Destiny"
もしくは"Four Pillars Astrology"と呼ばれているように、既に世界的に使用されている。中国では、「子平」「三命」「命学」「命理」「八字」などといわれている。 |
| 沿革 |
 |
1100年代、南宋の徐居易(徐子平)の書が文献考証的に四柱推命の最古となるため、徐子平が命学の祖といわれている(一説には、命理の始まりは、戦国時代(紀元前400年~
200年頃)の蘭台御史(天子の秘書官)の珞琭子であるとされている)。続いて1200年代に徐大升により『淵海子平』(えんかいしへい)という書が著され、1368年頃、明の軍師・政治家であった劉基(劉伯温)が『滴天髄』(てきてんずい)という書を著したとされている |
日本における
四柱推命 |
 |
日本には江戸時代中期に移入された。文政年間、仙台の儒学者桜田虎門が『推命書』という名称で『淵海子平』の訳本を出したのが、考証的に最古の書である。しかし桜田虎門は四柱推命に対する専門知識がなかったとも言われており、翻訳の質の点では疑問も残るとする評価もある。現代では阿部泰山流、高木乗流などがあるようである。粟田泰玄は阿部泰山流である。なお四柱推命に流派などない、という立場で武田考玄という研究者も活躍した。 |
|
|
|
|
|
|