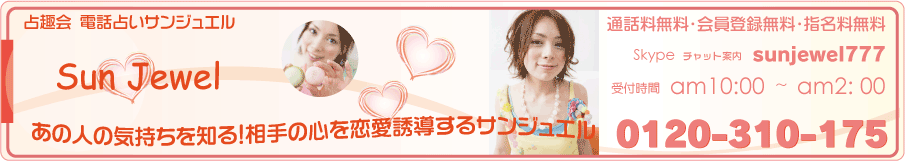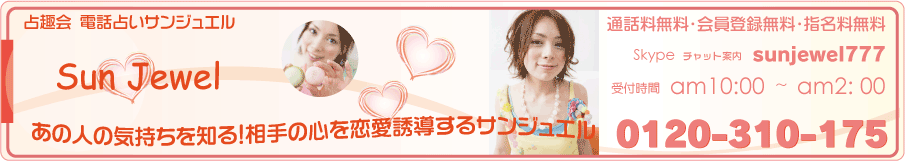| 命系占術 |
| 歴史 |
 |
西洋占星術の起源はバビロニアである。バビロニアでは紀元前2千年紀に天の星々と神々を結びつけることが行われ、天の徴が地上の出来事の前兆を示すという考え方が生まれたのである。 |
| 始祖 |
 |
不明 |
|
| 西洋占星術とは |
 |
西洋占星術(せいようせんせいじゅつ)は、西洋諸国で発達してきた占星術の体系である。ヘレニズム時代に成立した体系が基盤となっており、一般的にはホロスコープを用いる。占う対象に影響を及ぼすとされる諸天体が、出生時などの年月日と時刻にどの位置にあるかをホロスコープに描き出し、それを解釈する形で占う。
近代になって一般に広まったサン・サイン占星術では、太陽のあるサインを基にして占う。日本の雑誌などでよく見かける十二星座を基にした星座占いは、これを通俗化したものである。占星術一般がそうであるように、西洋占星術もまた、近代的な科学の発展に伴って「科学」としての地位から転落し、科学史などでは疑似科学に分類されるのが一般的である。
|
| 沿革 |
 |
現代にも引き継がれている星位図を描く占星術は、天文学が発達し、惑星の運行に関する知識が蓄積していった紀元前1千年紀半ば以降になって興った(この頃も含め、古来、天文学と占星術の境界の曖昧な時代は長く続いた)。
元々は暦のために整備された獣帯を占星術と結び付けることも、そのころに行われた。現存最古の星位図は、楔形文字の記録に残る紀元前410年の出生星位図(ある貴族の子弟の星位を描いたもの)である。ただし、この時点では、後のホロスコープ占星術に見られる諸概念はほとんど現れていなかった。 |
占星術と科学
|
 |
バビロニアでも部分的には見られたことだが、ヘレニズム時代以降に占星術の適用範囲は、実質上科学と位置づけられるもの全てに拡がった。すなわち、植物学、化学(錬金術)、動物学、鉱物学、解剖学、医学などである。
天上の星々は地上の諸々の物質との照応関係を持つものとされ、星々に対応する金属(太陽と金、水星と水銀など)、鉱石(これが誕生石の起源になったという説もある)などが定められた。
また、人体との照応関係をもとに占星医学(Iatromathematica)も発達し、その治療に用いる薬草類の研究が天体植物学として体系化された。さらに、マニリウスは全5巻の『アストロノミカ』の第4巻で、占星地理学(世界の地域を十二宮に対応させる)を論じている。
|
|
|
|
|
|
|